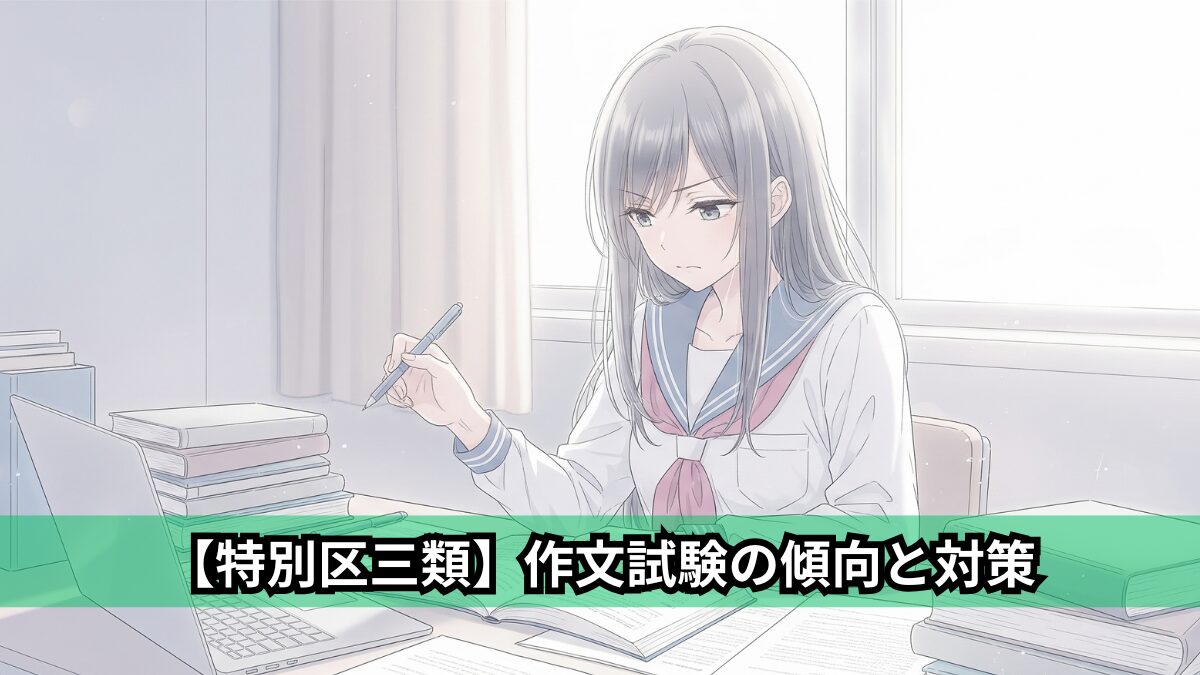特別区三類の採用試験合格に向けて、教養科目の勉強に励んでいることと思います。 しかし、そんな中で「作文試験」の対策を、つい後回しにしていませんか?
- 「教養試験に追われて、作文対策まで手が回らない…」
- 「そもそも何を書けばいいのか、テーマの意図すら分からない」
- 「一人で書いてみても、この内容で評価されるのか不安しかない」
もし一つでも当てはまるなら、この記事はあなたのためのものです。 実はこの作文試験こそ、筆記試験の点数だけでは測れない「あなたの人柄」をアピールし、合否を左右する超重要な科目なのです。
この記事では、そんな特別区三類の作文試験について、過去問の傾向分析から、すぐに使える「合格の型」、高評価を得られる模範解答、そして今日からできる勉強法まで、あなたの全ての不安を解消するために必要な情報を、余すことなく徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、作文への苦手意識が「これなら書ける!」という自信に変わっていますよ!
▼特別区三類の試験内容については、下記の記事で詳しくまとめています。はじめて受験する方は読んでおくといいでしょう。
特別区三類 作文試験の概要
特別区三類(高卒)の作文試験は、自分の思いや経験を文章にして伝える筆記試験です。
ただ単に文章を書けば評価されるのではなく、課題を正しく読み取り、自分の経験や体験を盛り込みつつ説明できるかといった知識の総合的な応用力が問われます。
| 試験時間 | 80分 |
|---|---|
| 文字数 | 600字~1000字 |
| 配点 | ※非公開 |
| 評価基準 | 【内容】 ・課題に適合しているか、長さは適当か ・中身のある作文か。幼稚すぎることはないか。 【表現】 ・わかりやすく、よくまとまっているか。 ・用語や表現は適切か。 【文字】 ・誤字やあて字が多すぎないか ・字体はていねいに読みやすく書かれているか。 |
80分という時間は、一見すると長く感じるかもしれません。しかし、テーマを理解し、構成を考え、実際に文章を書き、最後に見直しをすることを考えると、決して余裕があるわけではありません。
時間内に指定された文字数をクリアし、かつ内容の濃い文章を書くトレーニングが必要になりますね。
また、評価基準を見ると、ただ文章が上手いかどうかだけでなく、
- 課題の意図を正確に理解しているか(内容)
- 論理的で分かりやすい文章が書けているか(表現)
- 読み手を意識した丁寧な字で書いているか(文字)
といった、様々な観点からチェックされることがわかりますね。特に「丁寧な文字」は、意識するだけで改善できる重要なポイントですよ。
過去問からわかる!頻出テーマ3つの分類と傾向
試験のルールがわかったところで、次はいよいよ過去問の分析です。
「一体どんなテーマが出るんだろう…」と不安に思うかもしれませんが、大丈夫です。
実は、特別区3類の作文テーマは、大きく3つのグループに分けることができるんです。この傾向を知っておくだけで、ぐっと対策がしやすくなりますよ。
①区政・まちづくりに関するテーマ
これは、あなたが特別区の現状や課題について、どれだけ関心を持っているかを問うテーマです。 特別区の一員として、当事者意識を持っているかが試されます。
- 2023年度:未来の区役所!あなたはどうつくる?
- 2018年度:住み続けたいまちづくりについて
これらのテーマに対応するには、日頃から自分が受験する区のホームページを見たり、広報誌を読んだりして、地域の課題(例:防災、子育て支援、高齢化など)について自分なりの考えを持っておくことが大切ですね。
②公務員の資質・職業観に関するテーマ
これは、「理想の公務員像」や「仕事への心構え」など、あなたの公務員としての適性や倫理観を見るためのテーマです。
「なぜ数ある仕事の中から公務員を、そして特別区を選んだのか」という根本的な問いに答える必要があります。
- 2024年度:区民の声を聴くことの大切さ
- 2019年度:これからの公務員に求められる資質について
「区民のために働きたい」という想いを、具体的な言葉で表現できるように準備しておきましょう。
③自己分析・経験に関するテーマ
これは、あなたのこれまでの経験を通じて学んだことや、あなた自身の強み・人柄を問うテーマです。
面接の自己PRを文章で行うイメージに近いですね。
- 2022年度:5年後になりたい自分とそれに向けて実行していくこと
- 2020年度:私が地域に対してできること
学生時代の部活動やアルバイト、ボランティア活動など、具体的なエピソードを交えて書くことで、あなたの人柄が採用担当者に伝わりやすくなります。
どんな経験がアピール材料になるか、事前に棚卸ししておくと安心です。
このように、特別区の作文は様々な角度からあなた自身を評価するテーマが出題されます。
▼なお、より詳しい過去問の一覧は、こちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。
合格レベルの作文はこう書く!模範解答を解説!
傾向がわかったところで、次はより具体的に「どうすれば合格レベルの文章が書けるのか」を見ていきましょう。
テーマ:「活気あるまちのためにあなたができること」
まず、このテーマの出題者は何を知りたいのでしょうか?
それは、「あなたが地域の未来について当事者意識を持ち、自身の強みを活かして貢献できる人材か」という点です。
「活気」という言葉は非常に漠然としているため、いきなり書き始めようとすると、内容が薄く、誰でも書けるようなありきたりな文章になってしまいます。
そこで、思考の第一歩として、あなた自身の言葉で「活気」を具体的に定義することが不可欠です。
例えば、「子どもたちの笑い声が絶えないまち」と定義してみる。あるいは、「高齢者が安心して外出できる、支え合いのまち」と定義するのも良いでしょう。
このように、あなただけの「定義」を定めることで、文章の軸がブレなくなり、オリジナリティが生まれます。そして次に、その定義した「理想のまち」の実現に向けて、あなたの経験や強みをどう活かせるかを考えるのです。
この「①定義づけ → ②自己PRとの接続」という思考プロセスが、合格答案への必須ルートとなります。
文章構成「型」
頭の中で考えがまとまったら、次はその内容を「伝わる文章」に落とし込む作業です。 採点者に最も評価されやすい、万能の構成「型」をご紹介します。
まず冒頭で、「私が考える活気あるまちとは〇〇だ。その実現のため、私の△△という強みを活かして貢献したい」というように、テーマに対するあなたの答え(結論)を明確に述べます。
次に、序論で述べたあなたの強み(△△)が、どのような経験から得られたのかを具体的なエピソードを交えて説明します。部活動、アルバイト、ボランティアなど、あなたの人柄が伝わる経験を挙げましょう。
最後に、その強みを活かして、特別区職員としてどのように貢献していきたいかを具体的に述べます。「〇〇といった事業に携わりたい」「△△という役割を担いたい」のように、未来への意欲を示すことで、文章を力強く締めくくります。
この「序論 → 本論 → 結論」というシンプルな構成が、最も論理的で説得力のある文章を生み出すのです。
模範解答例
(序論)私が「活気がある」と感じるまちは、公園や商店街で、お年寄りから小さな子どもまで、色々な世代の人たちが自然に挨拶を交わし、楽しそうに話しているまちだ。そうした何気ない日常の繋がりこそが、本当の豊かさだと思うからだ。その実現のために、私は高校生活でのボランティア活動を通じて身につけた「相手の気持ちを考えて、話を深く聞く力」を活かして、まちに貢献したい。
(本論)私は高校に入学してから、地域の高齢者施設で話し相手のボランティアを続けている。初めの頃は、何を話していいかわからず、うまく会話が続かなかった。年の差がありすぎて、共通の話題を見つけるのが難しかったからだ。気まずい沈黙が流れることもあり、自分のコミュニケーション能力のなさに落ち込んだ。しかし、諦めずに通い続け、まずは笑顔で相槌を打ちながら、相手の話を一生懸命聞くことから始めた。ある日、いつも静かに窓の外を眺めている方が、私が着ていた制服を見て「私の孫も同じ高校だったんだよ」と話しかけてくれた。私はその言葉が嬉しくて、学校での出来事や部活動の話をたくさんした。すると、その方もご自身の若い頃の話や、このまちの昔の様子を、とても嬉しそうに語ってくれた。この経験から、ただ話すだけでなく、相手に心から興味を持って質問することが、心を開いてもらうために何より大切だと学んだ。そして、お年寄りの方が持つ思い出や知識は、教科書には載っていない、私たちのまちの「生きた歴史」であり、地域の宝物なのだと気づかされた。
(結論)もし特別区の職員になることができたら、この「深く聞く力」を仕事に活かしたい。例えば、地域のイベントを企画する際には、多くの住民の方から「どんなことがしたいか」「どんなまちになったら嬉しいか」という意見を丁寧に聞いて回りたい。そして、ボランティアで感じた世代をつなぐことの大切さを形にしたい。お年寄りの方に先生になってもらって、昔の遊びや地域の歴史を子どもたちに教えてもらうような交流会を開いてみたい。世代と世代をつなぐことで、みんなが「このまちが好きだ」と心から思えるような、温かい活気のあるまちづくりに貢献することが私の目標だ。
テーマ:社会に貢献することについて、具体的に述べなさい。
このテーマで採用担当者が見たいのは、決して壮大なビジョンや専門知識ではありません。
「あなたが『社会』や『貢献』という言葉を、どれだけ自分事として、具体的に捉えられているか」、その一点に尽きます。
多くの受験生が「世界平和に貢献したい」「環境問題の解決に貢献したい」といった大きな話を書こうとして、内容が薄っぺらくなり失敗します。
合格への鍵は、「貢献」のスケールを、自分の手の届く範囲までぐっと引き寄せることです。
「社会」を「自分のクラス」や「部活動のチーム」「アルバイト先」と読み替え、そこであなたが起こした「小さな、しかし具体的な貢献」を語ることが、最も評価されるのです。
文章構成「型」
このテーマでも、必勝の構成「型」は同じです。
冒頭で、「私にとって社会貢献とは、大きな偉業を成すことではなく、目の前にいる人の小さな『困った』を解決する手伝いをすることです」のように、あなた自身の言葉で定義します。そして、それを学んだ経験を簡潔に示します。
高校生活(文化祭、部活動など)での具体的な体験を述べます。重要なのは、「課題の発見 → あなたの行動 → 結果・変化」の流れを明確に書くことです。華々しい成功体験である必要は全くありません。
その経験を通じて、社会貢献について何を学んだのかをまとめます。そして、その学びを、特別区の職員としてどう活かしていきたいか、未来への熱意と覚悟を示して締めくくります。
模範解答例
(序論)私にとって「社会に貢献する」とは、特別な能力で偉業を成し遂げることではなく、自分の役割を責任をもって全うし、身近な人の「困った」や「大変」を少しでも軽くすることだと考えている。私はその大切さと喜びを、高校の文化祭で裏方の仕事を担当した経験から学んだ。
(本論)私のクラスは劇を発表することになり、私は大道具係に立候補した。主役や監督のように表舞台に立つわけではないが、物語の世界観を作る重要な役割だと考えたからだ。しかし、作業は想像以上に大変だった。デザイン担当と意見が食い違うこともあれば、予算と時間の制約の中で、必要な資材を集めるのに走り回る日も続いた。特に大変だったのは、公演前日に背景の壁の一部が壊れてしまった時だ。皆が諦めかけたが、私は同じ係の仲間と手分けをして、夜遅くまで修復作業にあたった。地味で、誰にも気づかれないような作業だったかもしれない。しかし、公演当日、舞台の幕が上がった瞬間の客席からの歓声と、舞台上で輝く仲間たちの笑顔を見た時、言葉にできないほどの達成感を感じた。私たちの作った舞台が、主役だけでなく、クラス全員、そして観客の感動を支えている。そう実感できた時、裏方として全力を尽くすことが、私の社会への貢献なのだと確信した。
(結論)特別区の職員の仕事も、一つ一つは地味で、区民の方から直接感謝される機会は少ない作業も多いのかもしれない。しかし、その一つ一つの仕事が、間違いなく区民の生活を支え、社会の土台となっている。私は文化祭で学んだ、誰かのために裏方として汗を流すことの喜びと責任感を忘れることなく、どんな仕事にも真摯に取り組みたい。そして、区民一人ひとりの「当たり前の日常」を支えるという形で、社会に貢献していく覚悟だ。
▼ここでは2014年度、2013年度のテーマをもとに解説しました。2024年度から2015年度までのテーマについても、下記の記事で解説しています。
合格レベルの作文が書けるようになる3ステップ対策法
模範解答を読んで「自分にも書けるかな…」と不安に思う必要はありません。
正しい手順でトレーニングを積めば、誰でも必ず合格レベルの文章を書けるようになります。この3つのステップを、今日から実践していきましょう。
STEP1:頻出テーマに関する知識をインプットする
作文でライバルと差がつく最初のポイントは、「具体性」です。特に「区政・まちづくり」に関するテーマでは、あなたがどれだけ特別区に関心を持っているかが試されます。
といっても、難しい政策を丸暗記する必要はありません。 まずは、自分が受験する区のホームページを覗いてみましょう。
- どんな取り組みに力を入れているか?(子育て支援、防災、環境問題など)
- 区長はどんなメッセージを発信しているか?
こうした情報を少し知っているだけで、「区民のために働きたい」というあなたの言葉に、ぐっと説得力が生まれます。
「この受験生は、ちゃんと私たちの区を調べてくれているな」と、熱意が伝わりますよ。
STEP2:自分の「経験」を洗い出し、ネタ帳を作る
作文は、あなたの人柄を伝える「もう一つの面接」です。
そのため、あなた自身の具体的なエピソードが何よりも強い武器になります。
そこでおすすめなのが、「ネタ帳」を作ることです。ノートやスマートフォンのメモ機能で構いませんので、これまでの自分の経験を書き出してみましょう。
- 部活動・サークル活動(例:チームで目標を達成した経験)
- 生徒会・委員会活動(例:課題解決のために仲間と協力した経験)
- アルバイト(例:お客様のために工夫した経験)
- ボランティア活動(例:社会貢献の喜びを感じた経験)
- 学業で頑張ったこと(例:苦手科目を克服した経験)
どんな些細なことでも構いません。
それぞれの経験について「①課題 → ②自分の行動 → ③結果・学んだこと」をセットでメモしておくと、どんなテーマが出題されても、引き出しに困ることはありません。
STEP3:「型」に沿って書き、必ず添削を受ける
知識とネタが揃ったら、いよいよ最後の仕上げです。 実際に、80分の時間を計って文章を書いてみましょう。
その際、必ず模範解答で解説した「序論 → 本論 → 結論」の構成「型」を意識してください。この型に沿って書くだけで、文章の論理性が飛躍的に高まります。
そして、書きっぱなしにしないこと。これが最も重要です。 書き上げた作文は、必ず誰かに読んでもらい、客観的な意見(添削)をもらいましょう。学校の先生や家族など、信頼できる人にお願いするのが第一歩です。
自分では完璧だと思っても、他人から見ると「話の繋がりが分かりにくい」「表現が幼稚に見える」といった弱点は意外とあるものです。 その弱点を一つずつ潰していく作業こそが、合格への最短ルートなのです。
▼下記の記事では模範解答例のほかに個別指導の特典をつけています。添削や相談できる相手がいないなら、ぜひ活用してください!
作文が苦手なあなたが落ちないための方法
先ほど、作文上達の鍵は「必ず添削を受けること」だとお伝えしました。
しかし、ここまで読んでくださった熱心なあなただからこそ、こんな新たな悩みや不安が出てきているのではないでしょうか?
- 「学校の先生は忙しそうで、何度もお願いするのは気が引ける…」
- 「そもそも先生は、公務員試験の採点基準に詳しいわけじゃない…」
- 「周りに頼れる人がいなくて、結局一人で抱え込んでしまいそう…」
その気持ち、痛いほどよく分かります。 独学での対策には限界があり、間違った方向に努力を続けてしまうのは、本当にもったいないことです。
そんなあなたのための「最終手段」として、私がこれまでの知識と経験を全て注ぎ込んで作成したのが、有料note『作文完全攻略パック』です。
このnoteは、単なる過去問解説集ではありません。 あなたの不安を「合格できる自信」に変え、本番で最高評価を得るための、まさにマンツーマンの個別指導です。
①過去10年分の全テーマ解説&模範解答を網羅
②回数無制限の作文添削&LINE相談
あなたの弱点を克服し、本番で確実に評価される「あなただけの合格答案」を、私と一緒に作り上げましょう。あなたの作文への不安を「自信」に変える最後のピースが、ここにあります。
まとめ:作文は「逆転の武器」。早期対策で合格を掴みましょう
今回は、特別区3類採用試験の作文対策について、概要から具体的な書き方、そしてトレーニング方法まで網羅的に解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返っておきましょう。
- 作文試験は、単なる文章力テストではなく合否を分ける「人物評価」の試験である
- 過去問のテーマには「①区政・まちづくり」「②公務員の資質」「③自己分析」という明確な傾向がある
- 「序論→本論→結論」の型と「あなた自身の具体的なエピソード」を組み合わせれば、合格答案は書ける
- 独学に限界を感じたら、プロの添削を頼るのが合格への最短ルートである
多くの受験生が教養科目の勉強に追われ、作文対策はどうしても後回しにしがちです。 だからこそ、この記事を読んで「やらなきゃ!」と思った今この瞬間から対策を始めるあなたが、ライバルに大きな差をつけることができます。
作文は、決してあなたの足を引っ張るものではありません。 正しく対策すれば、教養試験の点数を覆すことさえ可能な「逆転の武器」になります。
あなたの努力が、最高の結果に結びつくことを心から応援しています!
▼作文試験の解説・模範解答例・個別指導の特典をつけているnoteはこちら!