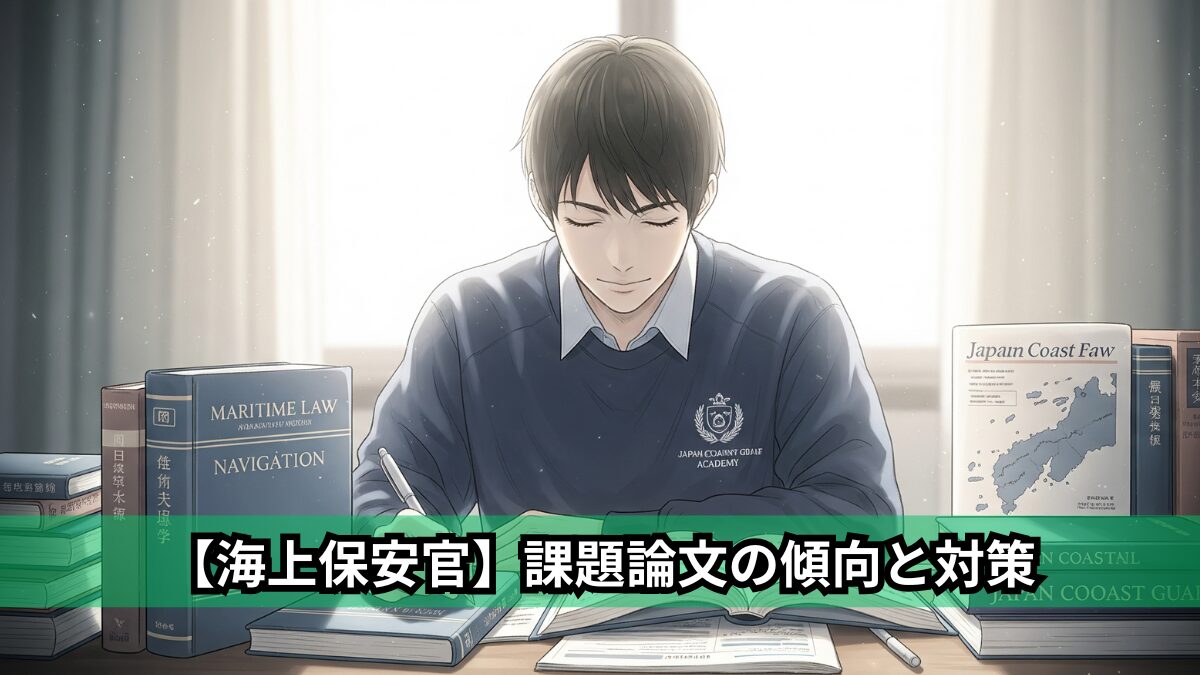海上保安官を目指す上で、多くの受験生が頭を悩ませるのが「課題論文」です。
「どんなテーマが出るの?」
「何文字くらい書けばいい?」
「そもそもどうやって対策すれば…」
といった不安や疑問を抱えていませんか?
この記事では、そんなあなたの不安を解消し、課題論文を苦手科目から「得点源」に変えるための具体的な方法を、過去問の徹底分析から最新情報まで交えて網羅的に解説します。
この記事を最後まで読めば、課題論文の全体像から合格答案の書き方まで、すべてが明確になりますよ。
海上保安官採用試験における課題論文の位置づけ
海上保安官採用試験の課題論文と聞くと、「文章を書くだけの試験でしょう?」と思うかもしれません。しかし、それは大きな間違いです。
課題論文は、あなたの合否を大きく左右する、極めて重要な評価項目と位置づけられています。
その理由は、主に2つあります。
1. 配点比率が非常に高い
まず、課題論文は全体の配点比率のうち「2/6」を占めています。
これは、基礎能力試験(3/6)に次いで高く、人物試験(面接、1/6)よりも2倍のウェイトが置かれているということです。
筆記試験の段階で、論文で高得点を確保することが最終合格への大きなアドバンテージになります。
2. 基準点(足切り)が設定されている
さらに重要なのが、「基準点」の存在です。
課題論文には合格の最低ラインである基準点が設けられており、これを1点でも下回ると、他の科目の点数がどんなに良くてもその時点で不合格となってしまいます。
2024年度の試験では、各問3点(満点6点)が基準点でした。
では、なぜこれほど課題論文が重視されるのでしょうか?
それは、この試験が単なる知識量ではなく、海上保安官として現場で必要となる「思考力」「判断力」「人間性」そのものを測るものだからです。
提示された課題を正しく理解し、論理的な構成で、説得力のある文章を書く能力は、そのまま職務遂行能力として評価されるのです。
試験の基本情報は以下の通りです。対策を始める前に、まずは敵を知ることから始めましょう。
| 試験時間 | 180分 |
|---|---|
| 問題数 | 2題 |
| 配点比率 | 2/6 |
| 満点 | 12点(各問6点) |
| 基準点 | 各問3点(2024年度) |
| 平均点 | 7.604点(2024年度) |
このように、課題論文は合否を分ける避けては通れない関門です。
次のセクションでは、この関門を突破するために、具体的な過去問の傾向を「出題形式別」に詳しく分析していきましょう。
あわせて読みたい
この記事では「課題論文」に絞って解説しますが、基礎能力試験や面接対策も含めた「海上保安官採用試験の全体像」を先に知りたい方は、以下のまとめ記事からご覧いただくと、より理解が深まりますよ。
【出題形式別】課題論文の過去問テーマと傾向分析
海上保安官採用試験の課題論文は、配点も高く、合否を分ける重要な試験です。
では、具体的にどのようなテーマが出題されるのでしょうか。
一見するとバラバラに見えるテーマですが、実は大きく2つのパターンに分類できます。この2つの「型」を理解することが、効率的な対策の第一歩です。
それぞれの特徴と過去の出題例を見ていきましょう。
① 政策理解・時事問題型テーマ
こちらは、政府全体の重要政策や、現代社会が抱える課題に対する理解度と、それに基づく自身の見解を論理的に述べる力が問われる形式です。
日頃からニュースや新聞に関心を持ち、物事を多角的に捉える視点と、自分なりの考えを構築する力が求められます。
過去の出題テーマ例
| 実施年度 | テーマ |
|---|---|
| 2025 | AI(人工知能)技術の活用のメリット・デメリットを踏まえ、身近な生活での有効な活用方法と注意点を論じる。 |
| 2024 | 国家公務員の男性職員による育児休業取得を、さらに促進するための効果的な方法を職場環境づくりの観点から論じる。 |
| 2023 | 組織内で発生するハラスメントのうち、特に問題視するものを一つ挙げ、その防止対策と事案発生時の対応について論じる。 |
| 2022 | 不明 |
| 2021 | 労働者にとって魅力ある職場となるための対策を一つ挙げ、その理由、実現する際の問題点と解消策について論じる。 |
ご覧いただくとわかるように、AI、働き方改革、ハラスメントといった、どの省庁の職員にとっても無関係ではいられない、現代的なテーマが出題されています。
海上保安庁独自の課題というよりは、国家公務員として持つべき幅広い視野と社会への問題意識が試されていると言えるでしょう。
② 現場対応・状況判断型テーマ
こちらは、あなた自身が海上保安部の指揮官になったと仮定し、限られた時間・情報・リソースの中で、人命救助などの任務をどう完遂させるかを問う、極めて実践的なシミュレーション問題です。
この形式では、以下の能力が総合的に評価されます。
- 複雑な条件を正確に読み解く読解力
- 情報を整理し、優先順位をつける論理的判断力
- 具体的な行動計画を立てる計画力
- なぜその判断に至ったのかを明確に説明する表現力
過去の出題テーマ例
| 実施年度 | テーマ |
|---|---|
| 2025 | 台風と火山噴火による二つの島の住民を、同時に避難させるための具体的な巡視船の運用計画と、その判断理由を説明する。 |
| 2024 | 無人航空機が発見した漂流中の漁船を、ヘリコプター、巡視船、巡視艇をどう運用して救助するかを説明する。 |
| 2023 | 集中豪雨で孤立した灯台の予備電源が切れる前に、職員と燃料をどう運び、燃料補給を維持するかの計画を立て説明する。 |
| 2022 | 不明 |
| 2021 | 洋上を航行中のコンテナ船で発生した急病人を、ヘリコプターと巡視船をどう連携させて救助・搬送するかの最善策を説明する。 |
まさに、あなたが海上保安官になったその日に直面するかもしれないリアルな課題ですね。
これらの問題を通じて、冷静な状況分析能力と、人命を預かる責任感、そしてリーダーシップの素養が厳しくチェックされます。
具体的なテーマ(過去問)は以下の記事で紹介しています。練習する際は活用してください!
合格ラインは?評価基準と目標点の考え方
過去の出題傾向がわかっても、「どのレベルの答案を書けば合格できるのか?」が一番気になりますよね。
課題論文の評価は、乗り越えるべき2つの壁で考えると分かりやすいです。
- 第一の壁:足切りラインである「基準点」
- 第二の壁:他の受験生と競う「平均点」
この2つの壁を理解し、具体的な目標点を設定しましょう。
第一の壁:足切りラインの「基準点」を絶対に下回らない
まず、最も重要なのが「基準点」です。これは合格のための絶対的な最低ラインで、これを下回ると他の科目の成績がどれだけ良くても不合格(足切り)となります。
 江本
江本2024年度の試験では、各問 3点(満点6点)が基準点でした。
評価は2名の試験官がA(3点)、B(2点)、C(1点)で採点し、その合計があなたの得点になります。つまり、2名の試験官から少なくとも「C評価(1点)」と「B評価(2点)」を貰わなければ、その時点で不合格となってしまうのです。
「とりあえず書けばOK」という甘い考えは通用しない、厳しい評価基準があることをまず認識しましょう。
第二の壁:合格を争う「平均点」を超える
基準点をクリアしても、それで合格できるわけではありません。次に意識すべきは「平均点」です。



2024年度の課題論文の平均点は 7.604点(12点満点)でした。
この数字から、8点以上を目標に設定するのが現実的な合格戦略と言えるでしょう。2問合計で8点ということは、1問あたり4点(例:試験官2名からB評価以上)を目指すイメージです。
目標点クリアの鍵を握る「3つの評価の観点」
では、どうすれば目標点をクリアできるのでしょうか。ポイントは、人事院が示す以下の「評価の観点」にあります。
海上保安官採用試験 課題論文 評価の観点
- 問題の趣旨
設問の意図を正しく理解し、問いに沿った解答をしているか。 - 思考・判断
広い視野から多角的に考察し、論理に矛盾なく、海上保安官として適切な判断・結論を下しているか。 - 構成・文章
文章全体が論理的で分かりやすく、正しい日本語で書かれているか。
簡単に言えば、
- 問いに正しく答えているか?
- 内容に深みと説得力があるか?
- 文章が読みやすく、構成がしっかりしているか?
という3つのポイントであなたの答案は採点されます。
課題論文で合格点を取るための3ステップ対策法
前のセクションで解説した評価基準をクリアし、目標である8点以上を獲得するために、具体的に何をすればよいのでしょうか。
ここでは、誰でも実践できる効果的な対策法を3つのステップに分けて解説します。
このステップ通りに進めれば、論文が苦手な方でも着実に実力をつけていくことができますよ。
STEP1:知識のインプット(情報収集)
質の高い論文を書くためには、まずそのテーマに関する知識、つまり「引き出し」を増やすことが不可欠です。
政策・時事問題型対策
日頃から新聞や信頼できるニュースサイトに目を通し、社会の動きに関心を持つことが基本です。
その上で、特におすすめしたいのが「海上保安レポート(海上保安白書)」です。海上保安庁が直面している課題や取り組みが公式にまとめられており、これ以上ない一次情報源となります。
ただ読むだけでなく、「自分ならどう考えるか?」という視点を持って読み進めましょう。
状況判断型対策
リアルな状況判断を下すには、海上保安庁という組織の能力を理解しておく必要があります。
「特大型巡視船」と「小型巡視船」では何が違うのか?「機動救難士」とはどんな専門家なのか?こうした基礎知識は、海上保安庁の公式サイトで学ぶことができます。
組織体制や保有する巡視船・航空機の概要を把握しておくことで、答案の解像度と説得力が格段に上がります。
STEP2:構成力のトレーニング(書き方の型を習得)
知識をインプットしたら、次はそれを論理的で分かりやすい文章にまとめる「構成力」を鍛えます。
どんなテーマにも応用できる、以下の「書き方の型」をマスターしましょう。
| 構成 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 序論 | 問題提起 結論提示 | 課題の背景を簡潔に述べ、「私は〇〇と考える」というように、まず自分の結論・主張を明確に示す。 |
| 本論 | 理由 具体例 展開 | 「なぜなら〜」と結論に至った理由を説明し、「具体的には〜」と事実やデータ、経験談を交えて説得力を持たせる。 |
| 結論 | 再度の結論提示 まとめ | 本論の内容を要約し、序論で述べた主張を再度強調する。今後の展望などを加えて締めくくる。 |
この「序論→本論→結論」という型を意識するだけで、文章は驚くほど整理され、論旨が明確になります。まずはこの型に沿って書く練習を繰り返しましょう。
STEP3:実践演習と添削(アウトプット)
知識をインプットし、書き方を学んだら、最後の仕上げは実践演習です。
まずは過去問を使い、試験時間(180分)を計って、実際に答案を作成してみましょう。本番と同じプレッシャーの中で書き上げる練習は非常に重要です。
そして、このステップが最も重要です。書いた答案は、必ず第三者に読んでもらい、客観的なフィードバック(添削)を受けましょう。
自分では気づけない論理の飛躍や、分かりにくい表現、誤字脱字などを指摘してもらうことで、答案の質は飛躍的に向上します。
大学のキャリアセンターや予備校の講座、信頼できる先生や先輩などにお願いしてみましょう。
「知識インプット → 型に沿って書く → 添削を受ける」
このサイクルを繰り返すことが、合格点を取るための最短ルートです。書いたら書きっぱなしにせず、必ず客観的な評価を得るようにしてください。
まとめ:課題論文を強みにして最終合格を掴み取ろう
今回は、海上保安官採用試験の課題論文について、出題傾向から具体的な3ステップ対策法まで詳しく解説してきました。
最後に、合格を掴むために最も重要なポイントを振り返りましょう。
- 課題論文は合否を分ける重要科目である
-
配点比率が高く(2/6)、「基準点」による足切りも存在します。決して軽視せず、十分な対策時間を確保しましょう。
- 出題には2つの「型」があることを理解する
-
「政策・時事問題型」と「現場対応・状況判断型」の傾向を把握することで、日々の情報収集や思考訓練の的が絞りやすくなります。
- 「インプット→構成→添削」のサイクルを回す
-
知識を学び、型に沿って書き、そして必ず第三者からの客観的な添削を受ける。このサイクルを繰り返すことだけが、着実に実力を伸ばす唯一の方法です。
課題論文は、多くの受験生が苦手意識を持つ科目だからこそ、しっかりと対策すれば大きな得点源となり、あなたの「強み」になります。
海上保安官に求められる思考力と判断力をこの試験で存分に発揮し、最終合格への道を切り拓いてください。
この記事が、あなたの夢の実現の一助となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!