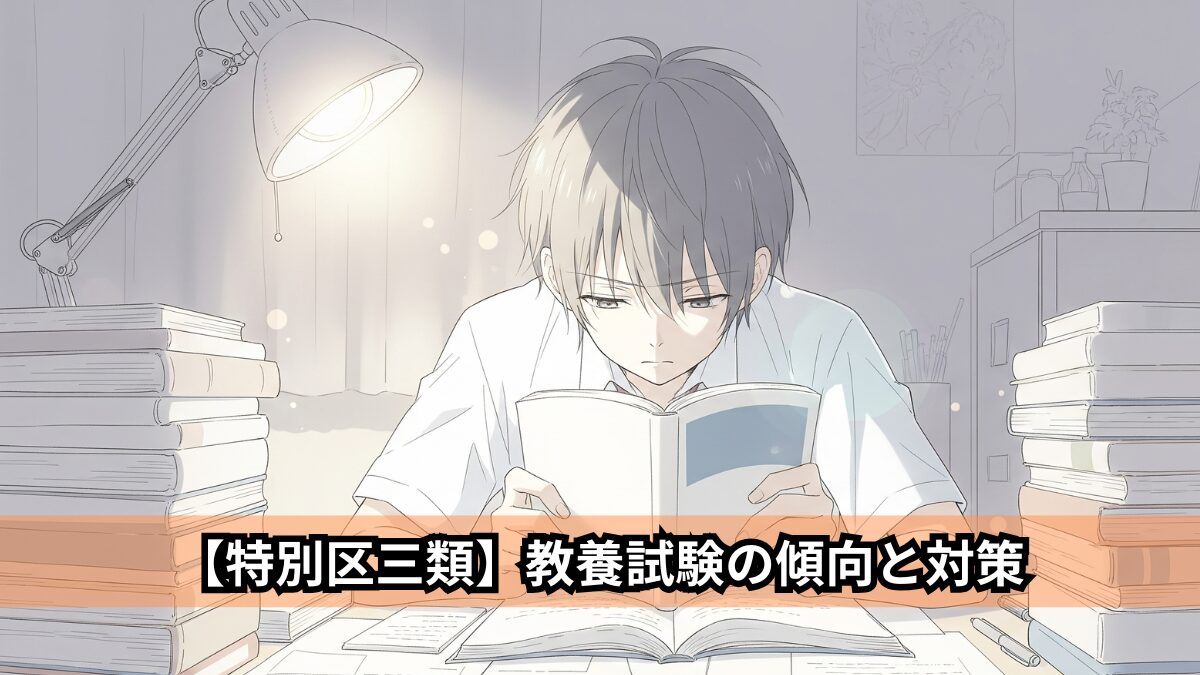特別区の公務員を目指しているけれど、
「教養試験って、科目が多くて何から手をつければいいか分からない…」
「数的推理とか苦手だけど、どう対策すればいいんだろう?」
「できるだけ効率よく勉強して、最短で合格したい!」
そんな悩みを抱えていませんか?
最初に試験全体の難易度や試験内容をまとめた下記の記事も読んでおくと理解が深まりますよ!
本記事では、その中でも特に多くの受験生が苦戦する「教養試験」にテーマを絞り、合格への最短ルートを徹底的に深掘りしていきます。
この記事を最後まで読めば、
- 教養試験の全体像と、目指すべき合格ライン
- 科目ごとの詳しい出題傾向と、対策のポイント
- 多くの合格者が実践してきた「具体的な勉強法の5ステップ」
これら全てが明確になり、あなたが今日から何をすべきかがハッキリと見えてきます。
教養試験は、正しい戦略と効率的な勉強法を知っているかどうかが合否を分けます。ぜひこの記事をあなたの「合格戦略の羅針盤」として活用し、ライバルに差をつける大きな一歩を踏み出してくださいね。
【高卒】特別区三類 教養試験の概要
特別区Ⅲ類(高卒)の公務員試験、合格への第一歩は、まず「敵を知る」ことから始まりますね。
教養試験は、公務員として働く上で必要な基礎的な知識や思考力を測るための大切な関門です。「科目が多くてどこから手をつけていいか分からない…」と不安に感じるかもしれませんが、安心してください。
まずは試験の全体像をしっかり掴んで、対策に向けての準備をしましょう。
試験時間・問題数・形式
教養試験の基本的な情報は以下の通りです。まずはこの全体像を頭に入れておきましょう。
| 試験時間 | 120分 |
|---|---|
| 問題数 | 50問 |
| 解答数 | 45問 |
| 難易度 | 高校卒業程度 |
| 出題形式 | 五肢択一式(マークシート) |
| 出題範囲※ | 一般知能㉘ 数的推理、判断推理、空間把握、資料解釈、文章理解 一般知識㉒ 社会科学、人文科学、自然科学 |
この表で最も重要なポイントは、解答方法の違いです。
思考力や判断力を問う「一般知能分野」の28問は、全員が必ず解かなければなりません。
一方で、高校までの学習内容が問われる「一般知識分野」は、22問の中から得意な17問を選んで解答することができます。
この仕組みを理解しておくだけで、「全部を完璧にしなくても良いんだ!」と少し気持ちが楽になりますよね。これが、効率的な学習戦略を立てる上での最初の鍵となります。
合格ボーダーは何割?目標得点を設定しよう
「で、結局何点取れば合格できるの?」という点が一番気になるところだと思います。
特別区の公式からは合格最低点(ボーダーライン)は発表されていません。しかし、例年の試験結果や合格者の情報から推測すると、おおよそ6割~7割が一次試験突破の目安となります。
つまり、解答する45問のうち、最低でも27問~32問程度の正解を目指す必要がありますね。
もちろん、年度によって難易度は変動するため、安全圏を狙うなら「7割以上(32問以上)」を目標に設定するのがおすすめです。
まずはこの目標得点を意識して、具体的な学習計画を立てていきましょう!
【科目別】教養試験の出題傾向と対策のポイント
試験の全体像と目標点数がイメージできたところで、次はいよいよ各科目の具体的な中身を見ていきましょう。
教養試験は、大きく分けて「①一般知能分野」と「②一般知識分野」の2つで構成されています。この2つの分野は性質が全く違うため、それぞれに適したアプローチで対策することが合格への近道です。
【最重要】一般知能分野の傾向と対策
まず、教養試験の核となるのが「一般知能分野」です。先ほど確認したように、この分野は28問すべてが必須解答であり、配点も高いため、ここでの得点が合否を大きく左右します。
出題科目は以下の通りです。
- 数的推理
- 判断推理
- 空間把握
- 資料解釈
- 文章理解(現代文、英文)
これらの科目は、単なる暗記ではなく、論理的な思考力や計算力、読解力を問う「考える力」が試されるのが特徴ですね。特に、数的推理や判断推理といった「数的処理」と呼ばれる分野は、苦手意識を持つ受験生が非常に多いです。
しかし、出題数が多い以上、避けては通れません。
大切なのは、基本的な解法パターンをしっかりと暗記し、使えるようにトレーニングを積むことです。最初は難しく感じても、繰り返し問題を解くうちに必ずコツが掴めてきますよ。
【効率重視】一般知識分野の傾向と対策
続いて、高校までの学習内容が問われる「一般知識分野」です。
こちらは22問の中から17問を選択して解答する形式のため、戦略的なアプローチが求められます。
出題科目は以下の3つの科学に分かれています。
- 社会科学(政治、経済、社会)
- 人文科学(日本史、世界史、地理、国語、思想)
- 自然科学(物理、化学、生物、地学)
見ての通り、科目数が非常に多く、出題範囲も膨大です。そのため、すべての科目を満遍なく勉強するのは非常に非効率。ここで重要になるのが「科目の選択と集中」です。
基本戦略は、自分の得意な科目で確実に得点し、苦手な科目は思い切って「捨て科目」にすること。
例えば、理系科目が苦手なら自然科学は最低限の勉強にとどめ、その分を社会科学や人文科学の暗記に時間を回す、といった計画が有効です。
「でも、どの科目を捨てていいか判断できない…」そう思いますよね。
実は、ただ闇雲に科目を捨てるのは得策ではありません。なぜなら、一見苦手に見える科目の中にも、頻繁に出題される“オイシイ”分野が隠れているからです。
例えば、自然科学の中でも「生物」や「化学」の一部は、複雑な計算が不要な暗記問題も出題されます。こうした「得点しやすい頻出分野」を知っているかどうかが、ライバルと差がつく大きなポイントになるのです。
この記事の後半では、具体的な勉強法のステップを解説しますが、その大前提として「出題傾向の分析」が不可欠である、ということを覚えておいてくださいね。
合格者が実践!教養試験の5ステップ勉強法
試験の全体像と科目ごとのポイントが分かったら、いよいよ実践です!
ここからは、多くの合格者が実践してきた、効率的な勉強の進め方を5つのステップで具体的に解説しますね。
この順番で進めていけば、学習の迷子になることなく、着実にゴールへ近づけますよ。
Step 1:効果的な学習計画を立てる
何事も、まずは計画から。特に、範囲の広い教養試験では「いつまでに、何を、どこまでやるか」という学習計画が不可欠です。
ポイントは、試験日から逆算してスケジュールを立てること。そして、完璧すぎない「無理のない計画」にすることです。
▼週の学習スケジュール例
- 平日(月〜金): 毎日1〜2時間、最重要の「一般知能」と、自分の苦手な「一般知識科目」を交互に学習する。
- 土曜日: 3時間程度、その週に学んだ内容の復習と、過去問演習に取り組む。
- 日曜日: 予備日(または休息日)。計画通りに進まなかった部分の調整や、思い切ったリフレッシュに使いましょう。
毎日コツコツ続けることが何よりも大切です。あなたのライフスタイルに合わせて、継続できる計画を立ててみてくださいね。
Step 2:参考書や問題集を揃える
計画が立ったら、一緒に戦う”武器”となる参考書や問題集を揃えましょう。
自分に合ったものを選ぶことが大切ですが、「どれを選べばいいか分からない…」という方は、多くの受験生に支持されている定番のものを選ぶのが安心です。
オススメの参考書はこちら。
Step 3:出題傾向を理解する
さあ、いよいよ勉強開始!…の前に、とても大切なステップがあります。
それは、本格的な学習に入る前に「出題傾向」をしっかり理解することです。
なぜなら、どの科目から、どの分野から手をつければ最も効率的かを知らずに勉強を始めるのは、ゴールの分からないマラソンを走るようなものだからです。
まずは過去問を3年分解いてみて、「どんな問題が出るのか」「どのくらいの難易度なのか」を肌で感じてみましょう。その上で、出題数の多い科目から優先順位をつけていくのが王道です。
▼科目ごとの出題数(近年の傾向)
| 科目 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 数的推理 | 6 | 5 | 5 |
| 判断推理 | 5 | 6 | 6 |
| 空間把握 | 3 | 4 | 4 |
| 資料解釈 | 4 | 4 | 4 |
| 文章理解 | 9 | 9 | 9 |
| 政治 | 3 | 3 | 3 |
| 経済 | 1 | 1 | 1 |
| 社会 | 1 | 1 | 1 |
| 日本史 | 2 | 2 | 2 |
| 世界史 | 2 | 2 | 2 |
| 地理 | 2 | 1 | 1 |
| 国語 | 4 | 4 | 4 |
| 思想 | 1 | 1 | 1 |
| 数学 | 0 | 0 | 0 |
| 物理 | 2 | 2 | 2 |
| 化学 | 2 | 2 | 2 |
| 生物 | 2 | 2 | 2 |
| 地学 | 1 | 1 | 1 |
このように、出題数には明確な偏りがあります。まずは出題数が多く、必須解答である文章理解・判断推理・数的推理から手をつけるのが、合格への最短ルートですね。
Step 4:出題頻度の高い分野から覚える
科目ごとの優先順位が決まったら、次はその「科目の中」で、さらに出題頻度の高い分野から集中的に学習を進めます。
たとえば、社会の出題範囲を分析すると「地球環境」はよく出ていますが、「社会保障」は出題がないことがわかります(下図参照)。

全範囲をゼロから網羅するのではなく、「よく出るところ」から完璧にしていくイメージです。
この「頻出分野」を知っているかどうかが、学習効率を何倍にも高める、最も重要な鍵となります。
科目別・分野別の出題範囲一覧を下記の記事で公開しています。あわせて確認してください。
Step 5:模擬試験で総復習する
学習が一通り進んだら、最後の総仕上げとして模擬試験を活用しましょう。模擬試験の目的は、単に実力を測るだけではありません。
- 本番の空気に慣れる
- 時間配分の練習をする
- 自分の弱点を最終チェックする
という3つの大きな目的があります。試験本番で緊張して実力が出し切れない…なんてことを防ぐためにも、必ず一度は経験しておきましょう。
そして最も大切なのは、模試を受けっぱなしにしないこと。
間違えた問題を徹底的に復習し、「なぜ間違えたのか」を分析して、本番までの残りの期間で確実に知識を補強していきましょう。
もっと深く知りたい方へ|頻出分野の徹底分析
さて、ここまで教養試験の攻略には「出題傾向を理解し、頻出分野から勉強すること」が何よりも重要だとお伝えしてきました。
「よし、過去問を分析して頻出分野を洗い出すぞ!」そう意気込むことは、とても素晴らしいことです。
しかし、その一方でこう思いませんでしたか?
「全科目の、過去何年分もの過去問を自分で分析するのは、正直言ってかなり大変だ…」
そうなんです。その作業には、膨大な時間と労力がかかってしまいます。貴重な勉強時間を、本来の問題演習ではなく分析作業に費やしてしまうのは、非常にもったいないですよね。
もし、その大変な分析作業をすべて終わらせ、あなたが今日からやるべきことを明確に示した”攻略本”があるとしたら…?
今回、あなたのそんな悩みを一発で解決するために、過去10年間の特別区Ⅲ類の教養試験を徹底的に分析し、全科目の「頻出分野」を完全網羅した攻略マニュアルを作成しました。
このマニュアルを読めば、
- どの科目の、どの分野が、どれくらいの頻度で出ているかが一目瞭然になります。
- あなたが真っ先に手をつけるべき分野が分かり、学習の迷いがなくなります。
- ライバルが時間を浪費している間に、あなたは得点に直結する勉強だけに集中できます。
あなたの努力を無駄にしないため、そして最短ルートで合格を掴むために、この詳細なデータを活用しない手はありません。
本気で合格したい方、そして効率的な学習でライバルに差をつけたい方は、ぜひ以下のリンクからその中身をチェックしてみてください。
科目別・分野別の出題範囲一覧を下記の記事で公開しています。あわせて確認してください。
特別区(高卒)教養試験に関するFAQ
最後に、受験生の皆さんからよく寄せられる質問にお答えします。
ここまで読んでまだ解消されていない疑問や不安があれば、ここでスッキリさせておきましょう!
Q1. 試験の難易度はどれくらいですか?
問題自体は、高校までに習った基礎的な内容が中心となります。そのため、一つひとつの問題が極端に難しいわけではありません。
ただし、出題範囲が非常に広いため、対策なしで合格するのは困難です。しっかりとした学習計画と、この記事で解説したような効率的なアプローチが合格の鍵を握ります。
Q2. 合格に必要な勉強時間の目安は?
もちろん、これはあなたの現在の学力や学習効率によって大きく変わります。
もし1日2時間の勉強時間を確保できるなら、半年(約6ヶ月)で約360時間になります。
少しペースを上げたり、休日の勉強時間を増やしたりすれば、十分に達成可能な時間ですね。大切なのは、毎日コツコツと学習を継続することです。
Q3. おすすめの参考書・問題集は?
ここでは、多くの合格者が実際に使ってきた人気の参考書・問題集をいくつかご紹介します。
オープンセサミシリーズ
公務員予備校東京アカデミーが監修している”初心者〜中級者向け“の参考書です。情報量が豊富でこれ1冊を覚えるだけでかなりの点数が取れます。
しかし、無駄な情報もそれなりに含まれているので出題傾向に沿って、必要な部分に絞って使うことがポイントです。
畑中敦子シリーズ
理系科目が苦手な人は取り組む価値のある参考書です。数的推理や判断推理、資料解釈について最もスタンダードな問題からやや応用レベルの問題まで、段階的にマスターできるように構成しております。
数学が不得意な方でも、解法パターンやテクニックを覚えることで、得意分野にすることは十分可能がコンセプト。
初めは解説を読んで解法をマスターし、それから自力で解けるようになるまで、繰り返し、手を動かして問題を解いてみてください!
公務員試験 合格の350シリーズ
公務員試験の過去問数年分を集約した問題集です。年別ではなく、科目別に編成されているため、勉強しやすい特徴があります。
試験種目は違いますが、問題レベル(内容)は同じなので、普通に使えます!
解説も丁寧なので、正文化しながら読み進め、必要箇所の知識を覚えたら、オープンセサミで肉付けしていくと効率よく勉強できるでしょう。
note
教養試験の出題範囲および過去問を集約した攻略マニュアルです。
「どの科目・分野から勉強すればいいんだろう?」「過去問をたくさん解きたいな」のような悩みを即解決できる1冊です。
Q4.教養試験の過去問はありますか?
また、下記記事でも過去問と使い方も解説しているので、参考にしてください。
Q5. 合格ボーダーラインは何割ですか?
年度や試験の難易度によって変動はありますが、合格をより確実なものにするためには、安定して7割以上(45問中32問以上)の得点を目指して学習を進めるのが理想的です。
 江本
江本その他、特別区三類に関する質問・相談はこちら!
まとめ:教養試験攻略の鍵は「頻出分野の分析」と「正しい勉強法」
今回は、特別区Ⅲ類(高卒)教養試験の全体像から、科目別の対策、そして具体的な5ステップの勉強法までを詳しく解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。
- 教養試験は「必須解答の一般知能」と「選択解答の一般知識」で構成される
- 合格の目標ラインは、まず「6割〜7割」を目指す
- 最重要科目は配点の高い「一般知能(特に数的処理と文章理解)」
- 合格の鍵は、出題傾向を分析し「頻出分野」から集中的に学ぶこと
- 学習は「計画→準備→分析→実行→仕上げ」の5ステップで進めるのが効率的
教養試験が多くの受験生を悩ませる最大の理由は、その「試験範囲の広さ」にあります。しかし、今日あなたがこの記事で学んだように、やみくもに全範囲を勉強する必要は全くありません。
出る可能性が高いところに絞って、そこを徹底的に固める。
この正しい戦略と勉強法を実践できるかどうかで、数ヶ月後の結果は大きく変わってきます。
あなたの貴重な時間と努力を、合格という最高の結果に結びつけるために。この記事が、その第一歩となれば、これほど嬉しいことはありません。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました!
科目別・分野別の出題範囲一覧を下記の記事で公開しています。あわせて確認してください。