- 「裁判所職員の面接って、何を聞かれるんだろう?」
- 「筆記試験の点数が良くても、面接で落ちるって本当?」
- 「配点が高いって聞いたけど、何から対策すればいいか分からなくて不安…」
裁判所職員(高卒)の最終合格を目指す上で、誰もがこのような壁にぶつかります。
筆記試験の対策とは違い、面接には明確な「正解」がないため、対策の進め方に戸惑うのは当然のことです。
しかし、ご安心ください。裁判所の面接試験にも、明確な「評価のポイント」と「攻略のための正しい手順」が存在します。
この記事では、
- 配点4割を占める面接試験の重要性
- 過去の受験者データに基づく頻出質問
- 合格を掴むための具体的な対策5ステップ
を、網羅的に、そして分かりやすく解説します。この記事を最後まで読めば、あなたの面接に対する漠然とした不安は、「何をすべきか」という具体的な行動計画へと変わるはずです。
▼面接カードの内容や書き方は以下の記事で解説しています!あわせてご覧ください。
まずは面接試験の概要を知ろう【配点は全体の4割】
効果的な対策を立てるには、まず試験を知ることが不可欠です。
ここでは、裁判所職員(高卒)の面接試験がどのような形式で行われるのか、その基本情報を確認しましょう。
面接試験の形式・時間・配点
| 試験時間 | 30分 |
|---|---|
| 面接官 | 3人 |
| 面接カード | あり |
| 配点比率 | 8/20 |
| 評価判定 | A~Eの5段階 |
特に注目すべきは「配点比率」です。全体の評価のうち、面接が占める割合は4割にも及びます。
これは他の公務員試験と比較しても非常に高い水準です。筆記試験で多少ビハインドがあっても、面接で高評価を得られれば十分に逆転が可能ですし、その逆もまた然りです。
評価はA〜Eの5段階|C評価では合格できない?
面接の評価は、A(非常によい)〜E(不良)の5段階で判定されます。そして、一般的に公務員試験の面接では、D評価以下は「足切り」となり、他の試験の成績に関わらず不合格となります。
また、最終合格者の多くはB評価以上を獲得しているのが実情です。C評価は「可もなく不可もなく」という評価であり、筆記試験の成績がよほど良くない限り、最終合格は厳しい戦いになります。
つまり、面接試験は「なんとか乗り切れば良い」というものではなく、「積極的にB評価以上を狙いにいく」という意識で臨む必要があるのです。
【過去問】裁判所職員(高卒)面接の頻出質問25選
面接対策の第一歩は、敵(=質問)を知ることです。ここでは、過去に裁判所職員(高卒)の面接試験で実際に聞かれた質問を、カテゴリ別に分けて紹介します。
これらの質問への回答を準備しておくことで、本番で頭が真っ白になるのを防ぎ、落ち着いて応答できるようになります。
カテゴリ1:あなた自身に関する質問(自己PR・長所など)
あなたの「人となり」や基本的なコミュニケーション能力、ストレス耐性などを確認するための質問です。
面接の冒頭で聞かれることが多いアイスブレイク的な質問も含まれます。
- 緊張していますか。
- 昨夜はよく眠れましたか。
- 会場まではどのようにして来ましたか。
- 自己PRをしてください。
- 自己PRに記載のある内容(例えば行動力)についてどのようなときにそれを感じましたか。
- 長所は何ですか。
- 長所を生かしたエピソードはありますか。
- 最後に意気込みを言ってください。
カテゴリ2:志望動機に関する質問(なぜ裁判所か?など)
志望動機は、面接で最も重視される項目の一つです。あなたの「本気度」と「裁判所への理解度」が厳しくチェックされます。
- 志望動機を教えてください。
- 志望動機を一言で言うならどうですか。
- 公務員になりたい理由は何ですか。
- 裁判所職員を知ったきっかけは何ですか。
- あなたが裁判所職員に向いているところはどこですか。
- 第一志望はどこですか。
- 併願はしていますか。
カテゴリ3:学生時代の経験に関する質問(学業・部活など)
高校生活で何に打ち込み、そこから何を学んだのかを問う質問です。面接カードに記載した内容から深掘りされることがほとんどです。
- 今の高校に進学した理由は何ですか。
- 高校時代に勉強以外で頑張ったことはありますか。
- (面接カード記載の)部活動で大変だったことは何ですか。
- (面接カード記載の)アルバイト経験で何を学びましたか。
カテゴリ4:裁判所・公務員に関する質問(知識・時事など)
裁判所の役割や業務内容について、どのくらい関心を持って情報収集しているか、また公務員としての自覚があるかを問う質問です。
- 裁判所職員に必要な資質や能力は何だと思いますか。
- 裁判所職員として何がしたいですか。
- 裁判所職員として働くうえで大切なことは何ですか。
- 裁判所職員の情報はどのようにして入手しましたか。
- 裁判を傍聴したことはありますか。
- 説明会には参加しましたか。
- 説明会の感想を教えてください。
 江本
江本見ていただくと分かる通り、奇抜な質問はほとんどありません。定番の質問に対して、いかに「自分自身の言葉」で「具体的なエピソード」を交えて語れるかが勝負の分かれ目になりますね。
▼この他にも以下の記事で多くの過去問を集約しています。ぜひ活用してください。
合格を掴む!裁判所職員 面接対策の5ステップ
面接の重要性と頻出質問を理解したところで、いよいよ具体的な対策方法について解説していきます。
何から手をつければ良いか分からないという方も、この5つのステップに沿って進めれば、着実に合格レベルの実力を身につけることができます。
STEP1:自己分析を行い「面接カード」を完璧に仕上げる
面接対策は、「自己PR・志望動機を作り込む」ことから始まります。
なぜなら、面接での質問は、あなたが事前に提出する「面接カード」に書かれた内容を元に展開されるからです。
逆に言えば、面接カードを戦略的に作り込んでおけば、面接の流れをある程度自分でコントロールできるのです。
■ 自己分析のヒント
- これまでの経験(部活、アルバイト、学校生活など)をすべて書き出す。
- それぞれの経験について「なぜそれを始めたのか?」「何が大変だったか?」「どう乗り越え、何を学んだか?」と自問自答を繰り返す。
この自己分析を通じて見えてきたあなたの強みや価値観を、面接カードに落とし込んでいきましょう。



面接カードは、いわば「面接の予告編」です。面接官に「この部分、もっと詳しく聞いてみたい!」と思わせるような、魅力的なキーワードを散りばめておくのがポイントですよ。
▼面接カードの具体的な書き方や項目別の例文はこちらの記事で詳しく解説しています。
STEP2:頻出質問への「回答の骨子」を準備する
自己分析と面接カードの作成が完了したら、次に先ほど紹介した「頻出質問」への回答を準備していきます。
この時のポイントは、回答を文章ですべて書き出して丸暗記するのではなく、話の要点となる「骨子(キーワード)」で用意することです。
■ 回答の基本フレームワーク
- 結論(Conclusion): 「私の長所は〇〇です」
- 理由(Reason): 「なぜなら、〜という経験で〇〇という力を培ったからです」
- 具体例(Example): 「具体的には、部活動で〜という課題があり、私は〜のように行動しました」
- 結論・貢献(Conclusion): 「この〇〇という強みを、裁判所職員として〜の業務で活かしたいです」
このフレームワークに沿って、各質問に対するあなた自身の経験を整理しておきましょう。
丸暗記した回答は、少し質問の角度を変えられるとすぐに答えに詰まってしまい、面接官にもすぐに見抜かれます。キーワードだけを頭に入れておき、あとは自分の言葉で話す練習をすることが重要です。
▼「この回答(志望動機・自己PR)でいいんだろうか・・・」と悩む場合は以下の記事を活用してください。
STEP3:裁判所への理解を深める(裁判傍聴・説明会)
過去問にも「裁判を傍聴したことはありますか」「説明会には参加しましたか」という質問があったように、裁判所はあなたがどれだけ「行動」して情報収集をしたかを見ています。
ホームページやパンフレットを読むだけでなく、実際に足を運ぶことで、志望動機に圧倒的な説得力と熱意が生まれます。
- 裁判傍聴: 実際の法廷の雰囲気や、裁判所職員(特に裁判所書記官)の仕事ぶりを肌で感じることができます。
- 説明会: 現場の職員から直接話を聞ける貴重な機会です。仕事のやりがいだけでなく、厳しさについて質問してみるのも良いでしょう。
これらの経験は、「傍聴した際、〇〇な場面で正確に記録をとる書記官の姿に感銘を受けました」というように、あなただけのオリジナルな志望動機や自己PRの根拠となります。
STEP4:「人に話す練習」を徹底的に繰り返す
回答の準備ができたら、次は声に出して話す練習です。
頭の中で考えているだけでは、スムーズに言葉は出てきません。いただいた情報にもある通り、「どんなにいいことを発言しても伝わらなければ意味がない」のです。
■ 具体的な練習方法
- スマホで録画: 自分の表情や声のトーン、話す速さを客観的に確認する。
- 時間を計る: 「1分で自己PR」など、時間を区切って簡潔に話す練習をする。
- 第三者に聞いてもらう: 家族や学校の先生に聞いてもらい、「話は分かりやすいか」「印象はどうか」などフィードバックをもらう。
最初は恥ずかしいかもしれませんが、この練習を繰り返すことで、本番でも自信を持ってハキハキと話せるようになります。
STEP5:模擬面接で最終チェック(最低1回は受ける)
対策の総仕上げとして、最低1回は模擬面接を受けましょう。模擬面接では、一人での練習では得られない多くの発見があります。
■ 模擬面接のメリット
- 本番さながらの緊張感を体験できる
- 自分では気づけない表情や仕草の癖を指摘してもらえる
- 回答に対して、プロの視点から深掘り質問をしてもらえる
練習相手は友人や家族でも良いですが、できるだけ予備校の先生や就職関連の先生など、公務員試験に精通した経験者にお願いするのが理想です。
客観的な評価をもらい、本番までに弱点を克服しておきましょう。
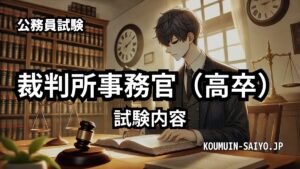
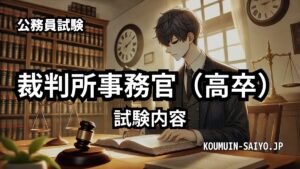
過去の質問項目や面接カード添削は下記の記事で紹介しています。
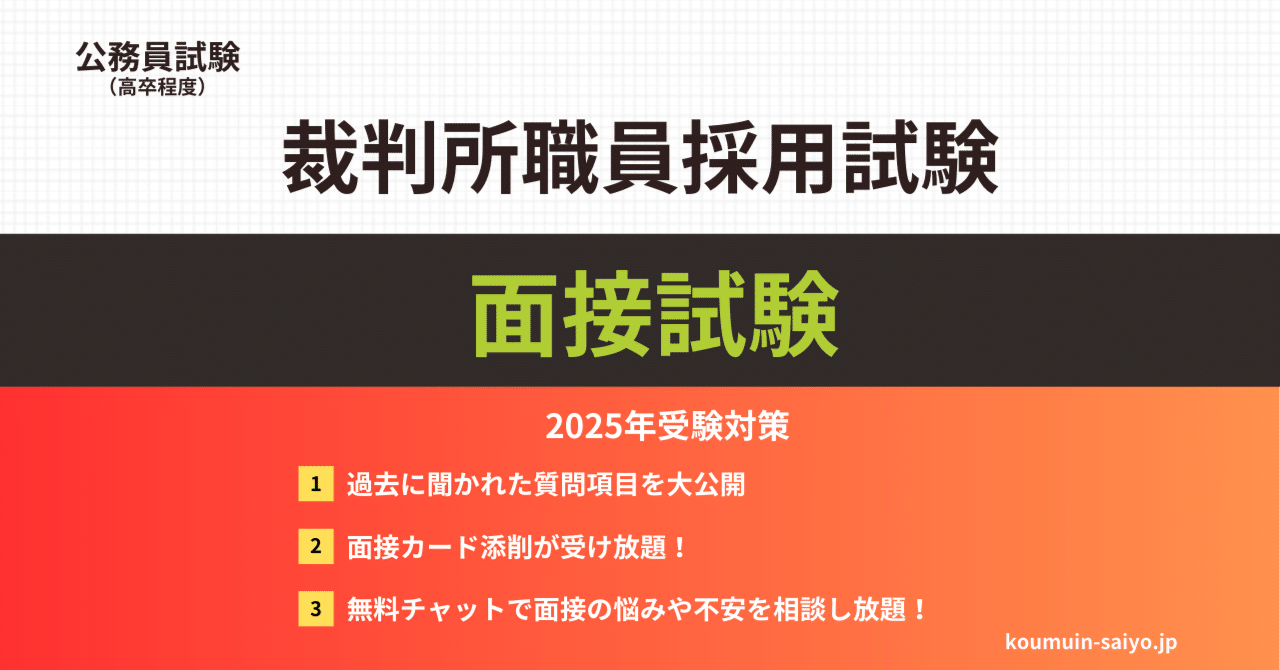
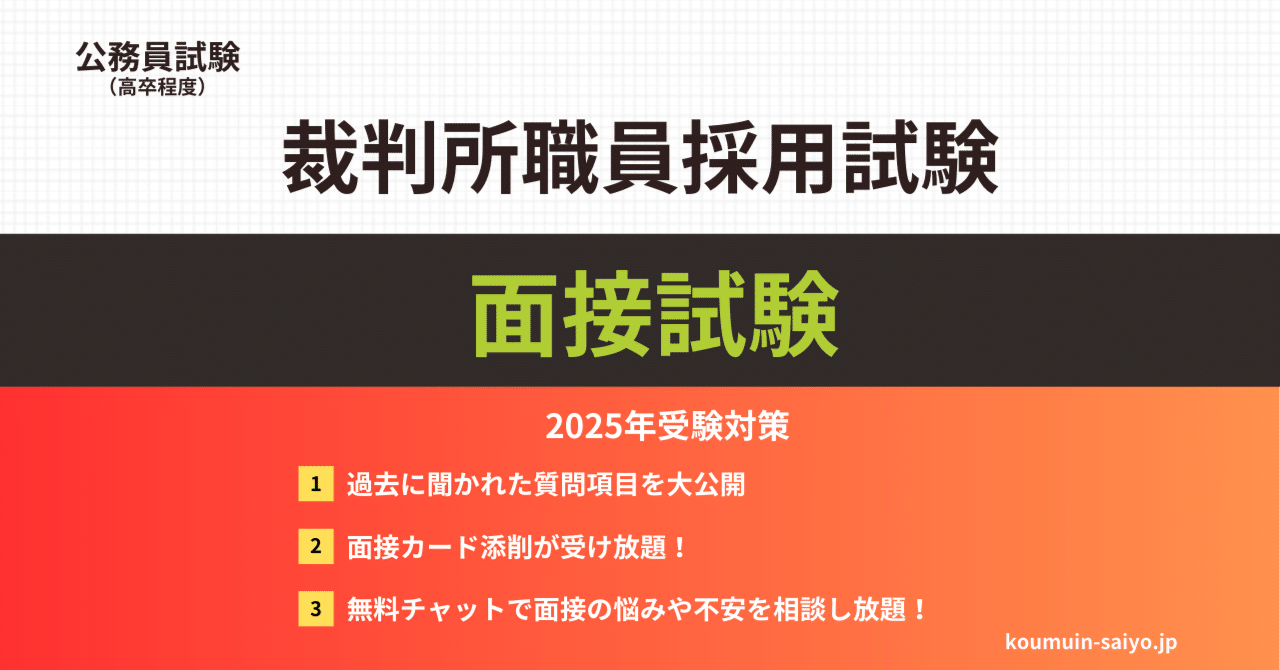
まとめ|早期対策でライバルに差をつけよう!
今回は、裁判所職員採用試験(高卒)の面接対策について、試験の概要から具体的な対策手順までを網羅的に解説しました。
面接対策を始める時期は早ければ早いほど良いです。近年、面接試験の重要度は増す一方であり、筆記試験の合格発表後に少し練習したくらいでは、ライバルと差をつけることはできません。
最後に、合格を掴むための5つのステップを振り返りましょう。
■ 面接対策5つのステップ
- 自己分析を行い「面接カード」を完璧に仕上げる
- 頻出質問への「回答の骨子」を準備する
- 裁判所への理解を深める(裁判傍聴・説明会)
- 「話す練習」を徹底的に繰り返す
- 模擬面接で最終チェック(最低1回は受ける)
面接は、筆記試験よりもやることが多く、上達にも時間がかかります。しかし、正しい手順で計画的に準備を進めれば、必ず自信を持って本番を迎えられます。
あなたのこれまでの努力が実を結ぶことを、心から応援しています。
▼面接の過去問や自己PR・志望動機の作り方・添削を以下の記事で解説しています。ぜひ活用してください。
▼その他、裁判所職員採用試験の概要や対策方法を以下の記事でまとめています。
