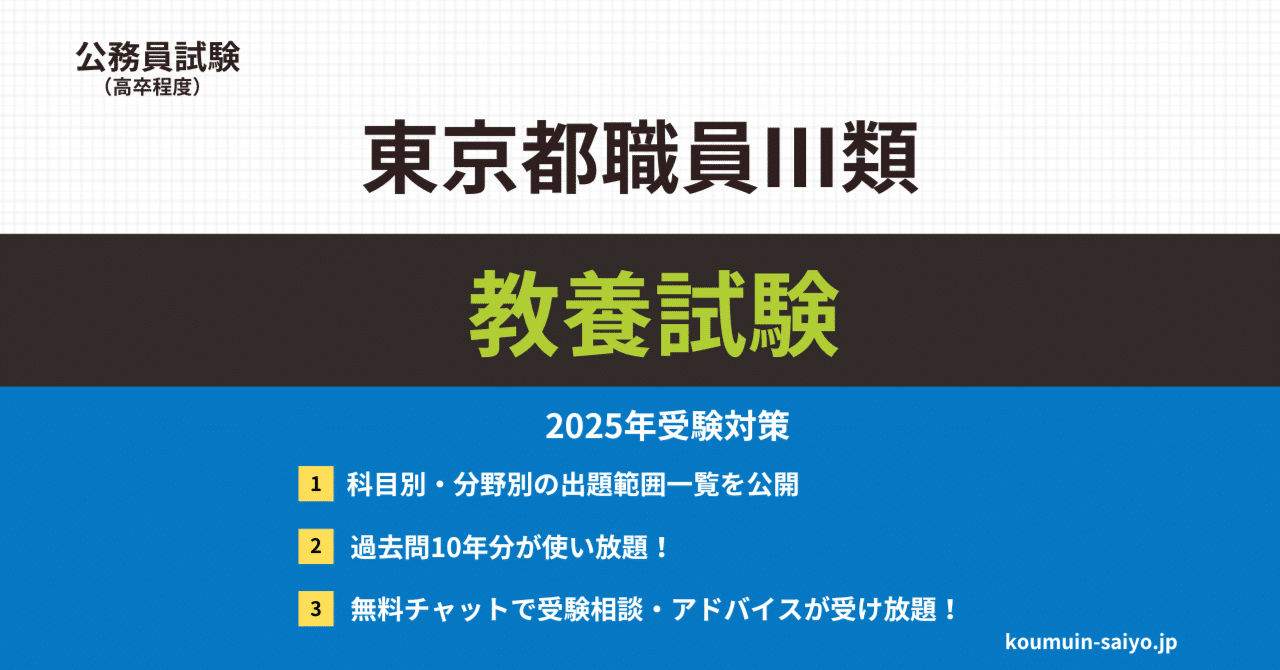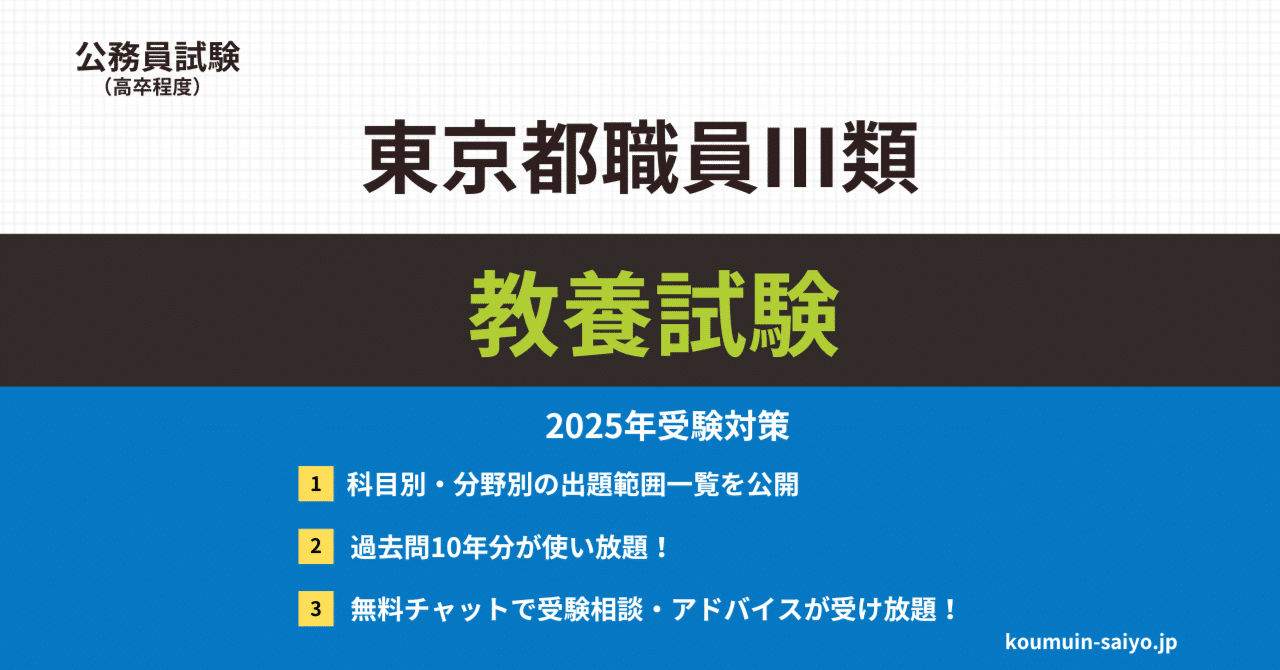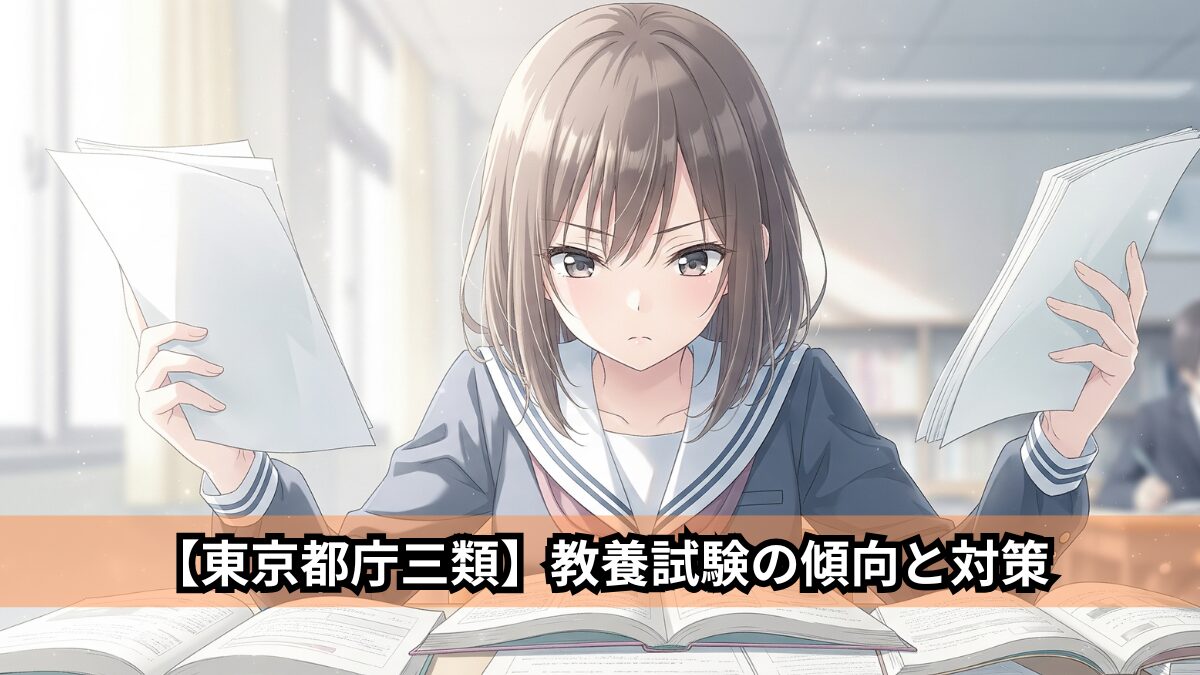東京都庁の職員を目指して勉強を始めたけれど、
- 「教養試験って科目が多くて、何から手をつければいいか分からない…」
- 「配点が高いっていう数的処理、どう対策すればいいんだろう?」
- 「できるだけ無駄な勉強はせず、効率よく合格点をとりたい!」
そんな悩みを抱えていませんか?
東京都職員Ⅲ類(高卒)採用試験の一次試験は、「教養試験」と「作文試験」で構成されていますが、合否を大きく左右するのは、間違いなくこの教養試験です。
なぜなら、教養試験の成績が一定の基準に達しない場合、作文試験は採点すらされないからです。
この記事では、そんな最重要関門である教養試験にテーマを絞り、合格への最短ルートを徹底的に解説していきます。
この記事を最後まで読めば、
- 教養試験の全体像と、目指すべき合格ライン
- 科目ごとの詳しい出題傾向と、学習の優先順位
- 多くの合格者が実践してきた「具体的な勉強のロードマップ」
これら全てが明確になり、あなたが今日から何をすべきかがハッキリと見えてきます。
教養試験の攻略は、正しい戦略と効率的な勉強法を知っているかどうかで決まります。ぜひこの記事をあなたの「合格戦略の羅針盤」として活用し、都庁職員への大きな一歩を踏み出してくださいね。
▼東京都職員三類の試験内容は以下の記事でまとめています。初めて受験する方は確認しておくといいでしょう。
東京都職員三類の教養試験概要
本格的な科目別の対策を始める前に、まずは「教養試験」がどのような内容で行われるのか、その全体像をしっかり確認しておきましょう。
基本情報を頭に入れておくだけで、学習計画がぐっと立てやすくなりますよ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験時間 | 120分(2時間) |
| 出題数 | 45問(全問必須解答) |
| 難易度 | 高校卒業程度 |
| 出題形式 | 五肢択一式 |
| 試験方式 | マークシート方式 |
| 合格基準 | 6割程度が目安 |
この中で、特に重要なポイントが2つあります。
一つ目は、「45問全問が必須解答」であるという点です。
公務員試験の中には、一部の問題を選択して解答できる形式(例:特別区)もありますが、東京都三類ではそれができません。つまり、どの科目からも逃れることはできず、幅広い知識が求められるということです。
二つ目は、合格のボーダーラインです。
公式に発表されているわけではありませんが、例年の傾向から合格には6割程度の得点が必要と言われています。
つまり、45問中27問以上の正解が、一次試験突破のための最低ラインとなりますね。もちろん、年度による難易度の変動も考慮すると、安定して7割(32問以上) を得点できる実力をつけておくのが理想です。
 江本
江本この「45問中27問」という具体的な数字を常に意識しながら、学習を進めていきましょう!
【科目別】教養試験の出題数と勉強の優先順位
教養試験の全体像が掴めたら、次はいよいよ科目ごとに出題傾向を分析し、勉強の優先順位を決めていきましょう。
以下の表は、過去3年間の科目別出題数をまとめたものです。これを見れば、どこに力を入れて勉強すべきかは一目瞭然ですね。
▼東京都職員三類 教養試験の出題数一覧
| 試験科目 | R6年度 | R5年度 | R4年度 |
|---|---|---|---|
| 数的推理 | 8 | 8 | 8 |
| 判断推理 | 7 | 7 | 7 |
| 資料解釈 | 5 | 5 | 5 |
| 文章理解 | 8 | 8 | 8 |
| 政治 | 2 | 3 | 2 |
| 経済 | 2 | 2 | 2 |
| 社会 | 2 | 1 | 2 |
| 日本史 | 2 | 2 | 2 |
| 世界史 | 2 | 2 | 2 |
| 地理 | 2 | 2 | 2 |
| 国語 | 1 | 1 | 1 |
| 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 化学 | 1 | 1 | 1 |
| 生物 | 1 | 1 | 1 |
| 地学 | 1 | 1 | 1 |
ご覧の通り、東京都三類の教養試験は、ここ数年、科目ごとの出題数がほぼ固定されています。
これは受験生にとって非常に大きなアドバンテージ。つまり、的を絞った対策が非常に立てやすいということです。
この傾向を踏まえ、大きく2つの分野に分けて対策を考えていきましょう。
【最重要】知能分野の出題傾向
まず、教養試験の得点の約6割を占める、最重要の「知能分野」です。
- 数的処理(数的推理、判断推理、資料解釈):合計20問
- 文章理解(現代文、英文):合計8問
この2分野だけで、全45問中28問を占めています。
特に、数学的な思考力が問われる「数的処理」は、苦手な受験生が多い一方で、配点が非常に高い最重要科目。数的処理を制する者が、教養試験を制すると言っても過言ではありません。
これらの科目は、知識の暗記というより「解き方のパターン」を理解し、使いこなすトレーニングが不可欠です。



最初は難しく感じても、諦めずに毎日コツコツと問題に触れ続けることが、合格への一番の近道ですよ。
【効率重視】知識分野の出頭傾向
続いて、高校までに学んだ知識が問われる「知識分野」です。
- 社会科学(政治、経済、社会):合計6問
- 人文科学(日本史、世界史、地理、国語):合計7問
- 自然科学(物理、化学、生物、地学):合計4問
こちらは合計で17問。知能分野に比べると配点は低いですが、暗記すれば確実に得点に繋がりやすいため、決して疎かにはできません。
ここで重要になるのが「勉強の効率化」です。
例えば、出題数が2問の「日本史」を対策するとしましょう。しかし、日本史の範囲は旧石器時代から現代までと、あまりに膨大です。これをすべて網羅しようとすると、時間がいくらあっても足りませんよね。
実は、公務員試験には「出やすい時代」や「頻出のテーマ」といった明確な傾向が存在します。例えば、文化史よりも政治史や外交史の方が問われやすい、といった具合です。
これは日本史に限った話ではありません。世界史も、地理も、政治・経済も同じです。膨大な範囲の中から、得点に直結する「頻出分野」を見極め、そこに学習時間を集中投下できるかどうか。
これが、知識分野で効率よく得点を稼ぐための最大の鍵となるのです。



詳しい出題分野は後述してあります!
合格者も実践!教養試験の鉄板ロードマップ
科目ごとの重要度が分かったら、いよいよ実践です。ここからは、多くの合格者が辿ってきた、効率的な学習の進め方を4つのステップでご紹介します。
この順番で進めていけば、膨大な試験範囲に惑わされることなく、着実に合格点へと近づけますよ。
Step 1:学習計画を立て、毎日の勉強を習慣化する
何よりもまず、「毎日必ず机に向かう」という習慣を作りましょう。
公務員試験は長期戦です。一夜漬けは通用しないため、コツコツと継続できる学習計画が不可欠になります。
▼学習計画のポイント
- 試験日から逆算する: 全体のスケジュールを把握し、月単位・週単位の目標を立てる。
- 無理のない計画を立てる: 最初から飛ばしすぎず、「毎日1時間」など、必ず継続できる時間から始める。
- 記録をつける: 学習時間や進捗を記録すると、モチベーション維持に繋がります。
まずは「勉強するのが当たり前」という状態を作ることが、合格への第一歩です。
Step 2:まずは過去問!敵を知り、己を知る
計画が立ったら、すぐに参考書を開くのではなく、まずは過去問を1〜3年分、時間を計って解いてみましょう。
目的は、点数を取ることではありません。
- どんな問題が出るのか(敵を知る)
- 自分がどのくらい解けないのか(己を知る)
この2つを肌で感じることが目的です。
最初に自分の現在地を把握することで、これからの学習の伸びを実感でき、モチベーションにも繋がります。東京都の過去問は、公式サイトで公開されていますよ。
Step 3:最重要の「数的処理」から徹底的に固める
自分の実力が分かったら、いよいよ本格的な学習のスタートです。真っ先に取り組むべきは、言わずもがな「数的処理」です。
数的処理は、解き方のパターンを理解し、体が覚えるまで反復練習が必要なため、最も時間がかかる科目です。試験直前期に慌てて手をつけても間に合いません。
このサイクルを、毎日少しずつでも良いので、ひたすら繰り返しましょう。数的処理を得意科目にできれば、合格は大きく近づきます。
Step 4:知識分野は「頻出テーマ」から効率よく潰す
数的処理の学習と並行して、「知識分野」の暗記も進めていきましょう。
ここで思い出してほしいのが、「学習の効率」というキーワードです。日本史や世界史の教科書を1ページ目から全て暗記しようとするのは、典型的な失敗パターン。
そうではなく、過去問の分析で明らかになった「頻出テーマ」から、一対一で知識を覚えていくのです。
例えば、「江戸時代の三大改革」「第一次世界大戦のきっかけ」など、テーマごとに重要な用語や流れを整理し、関連する過去問を解いて知識を定着させます。
この「出るトコ絞り」ができるかどうかが、ライバルと差をつける最大のポイントになります。
もっと深く!科目超別「頻出テーマ」を完全網羅したい方へ
さて、学習ロードマップの中で「知識分野は頻出テーマから潰していくのが鍵」とお伝えしました。
そう言われても、「その『頻出テーマ』が分からないから苦労してるんだ…」というのが受験生の本音ですよね。
例えば、これは都庁の「人文科学(日本史)」における過去10年間の出題テーマを分析したデータです。


いかがでしょうか。これを見れば、「近世」よりも「中世」や「近現代」の方が圧倒的に狙われやすい、という明確な出題の偏りが一目瞭然です。
日本史の勉強を始めるなら、教科書の1ページ目からではなく、この表で「1」がついている時代やテーマから手をつけるのが、どう考えても効率的ですよね。
そして、このような“出題されやすいテーマ”は、日本史だけでなく、世界史、地理、政治、経済…もちろん、最重要の数的処理にも、明確に存在します。しかし、この詳細な分析を、忙しいあなたが全科目分行うのは現実的ではありません。
その膨大で面倒な分析作業は、すべて僕にお任せください。あなたのそんな悩みを一瞬で解決するため、過去10年の東京都職員三類の教養試験を徹底的に分析し、全科目の「頻出テーマ」を完全網羅したデータを作成しました。
このデータを理解すれば、あなたはもう「どこから勉強すればいいか」と悩む必要は一切ありません。ただ、示された最短ルートをまっすぐに進むだけで、合格に必要な知識が面白いほど身についていきます。
ライバルが分厚い参考書と格闘している間に、あなたは得点に直結する勉強だけに集中し、一気に差をつけてしまいましょう。
▼詳しくは下記の記事で解説しています。
東京都職員三類 教養試験に関するFAQ
最後に、多くの受験生が抱える疑問や不安について、Q&A形式でお答えします。
ここで最後の疑問をスッキリ解消して、迷いなく学習をスタートしましょう!
Q1. 試験の難易度はどれくらいですか?
一つひとつの問題が奇問・難問というわけではありません。しかし、出題範囲が非常に広いため、無策で臨むと全く歯が立たないでしょう。
この記事で解説したように、出題傾向に沿って的を絞った対策ができるかどうかが、得点を大きく左右します。
Q2. 合格に必要な勉強時間の目安は?
もちろん、これは個人の学力や学習ペースによって変動します。
大切なのは時間の総量よりも、「毎日コツコツ継続すること」です。1日2時間の勉強を半年続ければ約360時間になります。まずは学習を習慣化することから始めましょう。
Q3. おすすめの参考書・問題集は?
特に、多くの合格者が利用している「オープンセサミシリーズ」や、数的処理が苦手な受験生から絶大な支持を得ている「畑中敦子シリーズ」、実践演習に最適な「過去問350シリーズ」などが有名です。
オープンセサミシリーズ
公務員予備校東京アカデミーが監修している”初心者〜中級者向け“の参考書です。情報量が豊富でこれ1冊を覚えるだけでかなりの点数が取れます。
しかし、無駄な情報もそれなりに含まれているので出題傾向に沿って、必要な部分に絞って使うことがポイントです。
畑中敦子シリーズ
理系科目が苦手な人は取り組む価値のある参考書です。数的推理や判断推理、資料解釈について最もスタンダードな問題からやや応用レベルの問題まで、段階的にマスターできるように構成しております。
数学が不得意な方でも、解法パターンやテクニックを覚えることで、得意分野にすることは十分可能がコンセプト。
初めは解説を読んで解法をマスターし、それから自力で解けるようになるまで、繰り返し、手を動かして問題を解いてみてください!
公務員試験 合格の350シリーズ
公務員試験の過去問数年分を集約した問題集です。年別ではなく、科目別に編成されているため、勉強しやすい特徴があります。
試験種目は違いますが、問題レベル(内容)は同じなので、普通に使えます!
解説も丁寧なので、正文化しながら読み進め、必要箇所の知識を覚えたら、オープンセサミで肉付けしていくと効率よく勉強できるでしょう。
note
教養試験の出題範囲および過去問を集約した攻略マニュアルです。
「どの科目・分野から勉強すればいいんだろう?」「過去問をたくさん解きたいな」のような悩みを即解決できる1冊です。
まずは書店で実際に手に取り、自分に合ったものを選んでみてください。
Q4.教養試験の過去問はありますか?
また、下記記事でも過去問と使い方も解説しているので、参考にしてください。
Q5. 合格ボーダーラインは何割ですか?
年度や試験の難易度によって変動はありますが、合格をより確実なものにするためには、安定して7割以上(45問中32問以上)の得点を目指して学習を進めるのが理想的です。



その他、東京都職員三類に関する質問・相談はこちら!
まとめ:教養試験の攻略は「頻出分野の分析」が9割
今回は、東京都職員三類(高卒)の教養試験について、その概要から具体的な学習のロードマップまでを詳しく解説しました。
最後に、この記事でお伝えした最も重要なポイントを振り返りましょう。
- 教養試験の合格ラインは「6割(45問中27問)」が目安
- 得点の約6割を占める「数的処理」と「文章理解」が最重要科目
- 学習は「計画→分析→数的処理→知識分野」の順番で進めるのが王道
- そして何より、膨大な範囲から「頻出分野」に絞って学ぶ戦略が合否を分ける
教養試験は、ただ闇雲に勉強時間をかければ合格できるほど甘くはありません。
しかし、今日あなたがこの記事で学んだように、正しい戦略に基づき、出る可能性が高いところに絞って学習を進めれば、必ず結果はついてきます。
この記事が、あなたの合格への道のりを照らす、一筋の光となれば幸いです。最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。