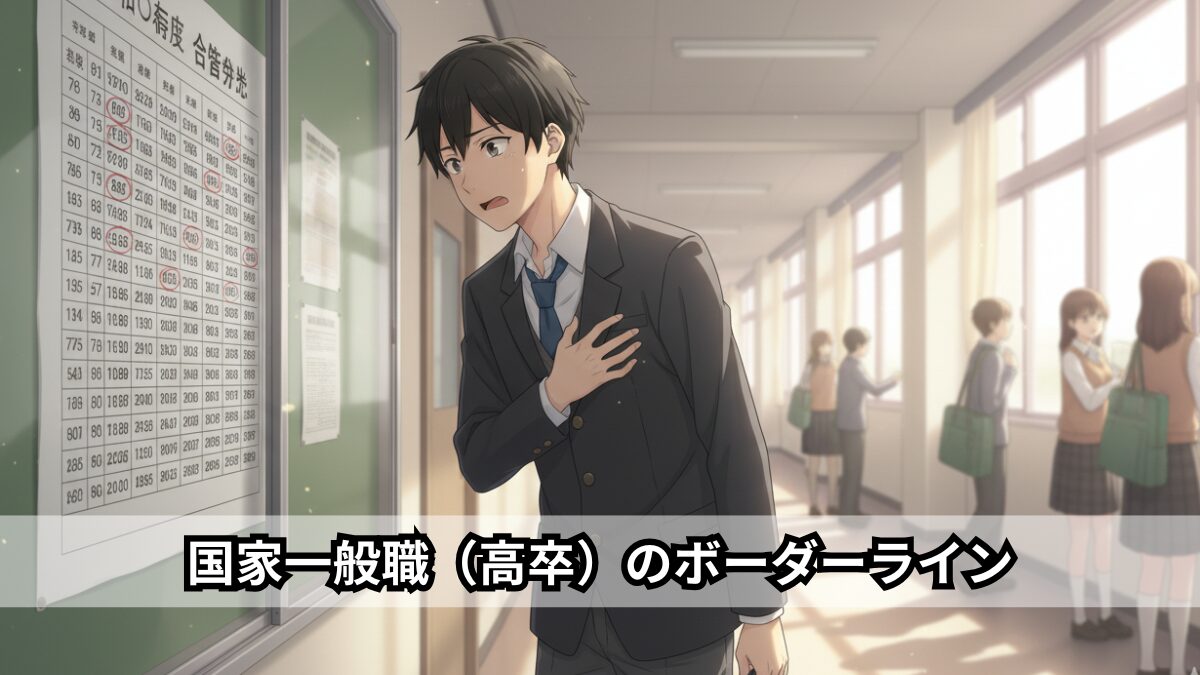国家一般職(高卒者試験)の合格を目指す上で、「ボーダーライン、つまり合格最低点は一体何点なんだろう?」と気になるのは当然のことですよね。
特に国家一般職は「事務」「技術」など区分が細かく、情報が探しにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、人事院が公表している公式データに基づき、国家一般職(高卒者試験)のボーダーラインを、試験区分ごとに整理しながら分かりやすく解説します。
この記事を読めば、あなたの受験する区分の具体的な目標点が明確になり、合格に向けた最短ルートの学習計画を立てることができますよ。
▼国家一般職(高卒)の概要や対策方法は以下の記事で解説しています。
国家一般職(高卒)のボーダーラインは複雑な「標準点」で決まる
まず最も重要な知識として、国家一般職の合否は、テストの正解数である「素点」ではなく「標準点」で決まります。
これは、簡単に言えば「偏差値」のようなもので、全受験者の中でのあなたの相対的な順位を示す点数です。
なぜこのような仕組みになっているかというと、毎年の試験難易度の違いによる有利・不利をなくし、公平性を保つためですね。
まずは「単純な点数ではなく、全体の中での位置が重要なんだな」と理解しておきましょう。
【区分別】国家一般職(高卒)の合格ボーダーライン一覧
過去の試験のボーダーライン(合格最低点)を区分別に見ていきましょう。
ここでは主要な「事務」「技術」「農業土木・林業」の3つのグループに分け、過去3年間の推移が比較しやすい形でまとめました。
ご自身の受験する区分の表で、目標点を確認してください。
事務区分
| 地域 | 2024 (1次 / 最終) | 2023 (1次 / 最終) | 2022 (1次 / 最終) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 213 / 445 | 290 / 481 | 288 / 480 |
| 東北 | 373 / 527 | 345 / 517 | 357 / 527 |
| 関東甲信越 | 333 / 503 | 363 / 515 | 361 / 537 |
| 東海北陸 | 327 / 514 | 338 / 504 | 350 / 512 |
| 近畿 | 307 / 509 | 345 / 508 | 378 / 525 |
| 中国 | 326 / 492 | 344 / 512 | 381 / 532 |
| 四国 | 312 / 509 | 320 / 497 | 340 / 525 |
| 九州 | 399 / 538 | 359 / 530 | 387 / 550 |
| 沖縄 | 397 / 579 | 437 / 580 | 425 / 592 |
技術区分
| 地域 | 2024 (1次 / 最終) | 2023 (1次 / 最終) | 2022 (1次 / 最終) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 343 / 444 | 291 / 431 | 259 / 419 |
| 東北 | 313 / 429 | 303 / 439 | 239 / 426 |
| 関東甲信越 | 321 / 422 | 306 / 427 | 255 / 431 |
| 東海北陸 | 321 / 412 | 298 / 422 | 239 / 413 |
| 近畿 | 351 / 451 | 330 / 446 | 286 / 433 |
| 中国 | 336 / 437 | 300 / 429 | 263 / 431 |
| 四国 | 318 / 419 | 289 / 431 | 262 / 454 |
| 九州 | 313 / 414 | 321 / 443 | 321 / 468 |
| 沖縄 | 351 / 498 | 299 / 463 | 267 / 471 |
農業土木・林業
| 区分 | 一次試験 | 最終合格 |
|---|---|---|
| 農業土木 | 284 | 385 |
| 区分 | 一次試験 | 最終合格 |
|---|---|---|
| 林業 | 252 | 375 |
【目標は何割?】ボーダーライン突破に必要な素点(正答数)の目安
さて、複雑な標準点のボーダーラインを見てきましたが、結局のところ「素点(=正解数)で何割くらい取ればいいの?」というのが一番知りたいポイントですよね。
もちろん、平均点は毎年変動するため「何点取れば絶対安心」とは言えませんが、過去の傾向から目標とすべき目安は明確にあります。
結論:まずは「素点6割」の突破を目指そう
結論として、どの区分を受験する場合でも、まずは一次試験(基礎能力試験、適性試験・専門試験)において「素点で6割」の正答を最初の目標にするのがおすすめです。
過去の平均点データを見ると、多くの区分で平均点が5割前後、つまり20点(40問中)あたりで推移しています。
合格者の多くが平均点+αの得点をしていることを考えると、「6割=24点」というのは、ボーダーラインを突破するための現実的かつ重要なラインと言えるでしょう。
実際に自分の素点が何点になるか気になる方は、人事院が公表しているデータを元に僕が算出した「標準点換算表」で確認してみましょう。
(補足)区分別!平均点と標準点のデータ
参考までに、人事院が公表している過去3年間の平均点と標準偏差のデータを区分別にまとめました。ご自身の受験する区分の平均点と、目標である「6割」のラインを見比べてみてください。
事務区分
| 実施年 | 基礎能力試験 | 適性試験 |
|---|---|---|
| 2024 | 17.994 (5.118) | 62.824 (21.347) |
| 2023 | 19.463点 (5.491) | 66.555点 (22.641) |
| 2022 | 18.347点 (4.854) | 64.157点 (19.892) |
技術区分
| 実施年 | 基礎能力試験 | 専門試験 |
|---|---|---|
| 2024 | 17.994 (5.118) | 13.953 (5.173) |
| 2023 | 19.463点 (5.491) | 17.001点 (5.659) |
| 2022 | 18.347点 (4.854) | 20.722点 (6.944) |
農業土木区分
| 実施年 | 基礎能力試験 | 専門試験 |
|---|---|---|
| 2024 | 17.994 (5.118) | 17.078 (6.807) |
| 2023 | 19.463点 (5.491) | 15.893点 (5.647) |
| 2022 | 18.347点 (4.854) | 18.494点 (6.609) |
林業区分
| 実施年 | 基礎能力試験 | 専門試験 |
|---|---|---|
| 2024 | 17.994 (5.118) | 20.167 (5.683) |
| 2023 | 19.463点 (5.491) | 19.697点 (6.565) |
| 2022 | 18.347点 (4.854) | 21.801点 (6.651) |
ボーダーライン突破を左右する3つの学習戦略
目標が「素点6割」と定まったら、次はその点数をどうやって取るか、ですね。
国家一般職(高卒)の試験は科目数が多いため、やみくもな勉強は禁物です。以下の3つの戦略が合格の鍵を握ります。
①配点比率を理解し、最重要科目に注力する
国家一般職(高卒)の最大の特徴は、区分によって試験ごとの重要度(配点比率)が大きく異なる点です。
| 試験科目 | 事務 | その他 |
|---|---|---|
| 基礎能力試験 | $$\frac{4}{9}$$ | $$\frac{2.3}{9}$$ |
| 専門試験 | – | $$\frac{4.7}{9}$$ |
| 適性試験 | $$\frac{2}{9}$$ | – |
| 作文試験 | $$\frac{1}{9}$$ | – |
| 人物試験 | $$\frac{2}{9}$$ | $$\frac{2}{9}$$ |
この表から分かるように、事務区分は「基礎能力試験」の配点が最も高い、技術・農業土木・林業区分は「専門試験」の配点が最も高い
ということになります。あなたが受験する区分の最重要科目に学習時間の多くを投下することが、最も効率的な得点アップ戦略です。
②頻出分野に絞り、完璧主義を捨てる
これは公務員試験全般に言えることですが、すべての科目のすべての範囲を完璧にする必要は全くありません。むしろ、それは不合格への道です。
どの科目にも、繰り返し出題される「頻出分野」と、ほとんど出ない「マイナー分野」が存在します。
貴重な勉強時間を最大限に活かすには、過去問を分析して「出るところ」を重点的に学習し、「出ないところ」は思い切って捨てる勇気を持ちましょう。
▼科目別に出題範囲を一覧かしています。詳しくは以下の記事をご覧ください。
③基準点(足切り)を回避する
国家一般職には、他の公務員試験と同様に「基準点(足切り)」制度があります。これは、ある試験種目の得点が基準点に満たない場合、他の科目が満点でも即不合格となる厳しいルールです。
一般的に、各種目の満点の3割程度が基準点とされています。「専門科目は得意だけど、教養科目は全く勉強しない」といった極端な学習計画は非常に危険です。
苦手な科目でも最低限の点数(3〜4割)は確保する、という守りの意識も忘れないようにしてくださいね。
まとめ:正しいボーダーラインを把握し、合格への最短ルートを描こう
今回は、国家一般職(高卒者試験)のボーダーラインについて、区分別に詳しく解説しました。
最後に、この記事の最も重要なポイントを振り返ります。
- 合否は素点ではなく「標準点」で決まる。
- 目標とすべき目安は、まず「素点で6割」を突破すること。
- 「配点比率」を理解し、自分の区分の最重要科目に集中することが合格の鍵。
自分の現在地とゴール(ボーダーライン)との距離が正確に測れていれば、あとはその差を埋める学習計画を立てるだけです。
ボーダーラインを把握したら、次はいよいよ具体的な科目対策ですね。まずは、多くの区分で重要となる「基礎能力試験」の対策から始めてみましょう!
▼基礎能力試験の勉強方法は以下の記事で詳しく解説しています。